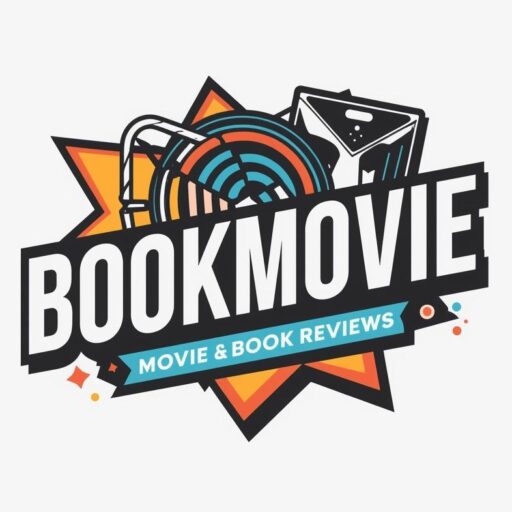「とにかく仕組み化 ── 人の上に立ち続けるための思考法は読むべき?」
「どんな人におすすめ?」
リーダーとして組織を率いる立場になったとき、多くの人が直面する悩みがあります。部下のやる気に頼る指導法、属人化した業務、再発する問題――。
こうした課題を解決するカギが「仕組み化」です。
安藤広大氏の著書「とにかく仕組み化 ── 人の上に立ち続けるための思考法」は、識学という独自の経営理論に基づき、人に頼らない組織づくりの本質を解説した一冊です。本書はベストセラー「リーダーの仮面」「数値化の鬼」に続くシリーズ作品として、より実践的な仕組み化の思考法を提示しています。
しかし、Amazonのレビューを見ると評価が大きく分かれています。「組織として最大価値を出すために最も重要な考え方」と絶賛する声がある一方で、「仕組み化の具体的方法が書かれていない」という批判も。この記事では、実際に読んだ人のレビューを徹底分析し、あなたにとって読む価値がある本かどうかを判断できる情報をお届けします。
とにかく仕組み化 ── 人の上に立ち続けるための思考法はこんな人におすすめ
本書は「リーダーの仮面」「数値化の鬼」を既に読んだ人に最適な一冊です。実際のレビューを分析した結果、読者の満足度は前提知識の有無によって大きく変わることが分かりました。
- 識学の基本概念を理解している人におすすめ
- 組織として成果を最大化したい経営者・管理職におすすめ
- 仕組み化の具体的な手順を求める人には合わない
本書は仕組み化のハウツー本ではなく、組織運営における思考法を深める本です。著者の他の著作を読み、その内容に共感できた人にとっては、実践で活用するためのルールづくりの考え方を学べる価値ある一冊となります。
とにかく仕組み化 ── 人の上に立ち続けるための思考法の基本情報
| 項目 | 情報 |
|---|---|
| タイトル | とにかく仕組み化 ── 人の上に立ち続けるための思考法 |
| 著者名 | 安藤広大 |
| 出版社 | ダイヤモンド社 |
| 発売日 | 2023年5月31日 |
| ページ数 | 320ページ |
| 価格 | 1,870円 |
| ISBN | 978-4478117743 |
とにかく仕組み化 ── 人の上に立ち続けるための思考法の要約とあらすじ紹介
本書は識学理論に基づき、人に依存しない組織運営の本質を解説しています。著者は株式会社識学の代表取締役社長として、3,000社以上の組織改革を支援してきた実績を持ちます。
これらのポイントを中心に、リーダーが身につけるべき仕組み化の思考法を320ページにわたって展開しています。従来の感情論や精神論とは一線を画す、合理的な組織論が特徴です。
要約ポイント1:属人化を排除する仕組みづくりの本質
本書が最も重視するのは、個人の能力や意欲に依存しない組織運営の実現です。多くの組織では「この人がいないと回らない」という状況が生まれがちですが、それは真の仕組み化ではありません。
著者は「人のやる気に頼る時点で、仕組み化は失敗している」と明言します。マネジメントとは人を動かすことではなく、誰が担当しても同じ成果が出る環境を整えることだと定義しています。
そのために必要なのは、明確なルール設定と権限の分配です。リーダーの役割は部下を励ますことではなく、迷いなく行動できる環境を作ることにあると述べられています。
要約ポイント2:人ではなくルールを改善する思考転換
問題が発生したとき、人を責めるのではなくルールを見直す――これが本書の核心的な主張です。多くの組織では、ミスが起きると担当者の責任を追及しがちですが、それでは根本的な解決になりません。
著者によれば、同じ問題が再発するのはルールが不完全だからです。人の注意力や責任感に頼る体制は、いずれ必ず破綻します。重要なのは、誰がやっても失敗しない仕組みを構築することです。
本書では、ルールを責める文化がなぜ組織を強くするのか、具体的な理論と共に解説されています。この考え方は従来の日本的経営とは異なり、合理的な組織運営を目指す人にとって新鮮な視点となるでしょう。
要約ポイント3:個人よりも組織としての成果を優先する価値観
本書は「個人として成果を上げるのか、組織としてより大きな成果を上げるのか」という根本的な問いを投げかけます。リーダーの役割は個人プレーヤーとして活躍することではなく、組織全体の成果を最大化することだと明確に述べています。
多くのリーダーが陥る罠は、自分が現場で動いてしまうことです。短期的には効率的に見えますが、長期的には組織の成長を妨げます。部下が自律的に動ける環境を作ることこそが、リーダーの最重要任務なのです。
著者は、組織人としての考え方を徹底的に学べると述べています。個人の努力や才能に頼る従来型の方法論から脱却し、システムとして機能する組織づくりの思考法が全編を通じて展開されています。
とにかく仕組み化 ── 人の上に立ち続けるための思考法を読んだ感想
本書は読者の前提知識によって評価が大きく変わる一冊です。識学の基本概念を理解している読者からは「伏線回収的な本」として高く評価される一方、初めて著者の本を読む人からは「抽象的で分かりにくい」という声が上がっています。
実際のレビューを見ると、「リーダーの仮面」「数値化の鬼」を既に読んでいる人は、本書の内容に深く納得し、実践に活用できると評価しています。一方で、仕組み化の具体的なハウツーを期待した読者は期待外れと感じる傾向があります。
本書の価値は、テクニックではなく思考法にあります。流行りの経営論とは逆方向を行く内容ですが、組織として最大の価値を出すための本質的な考え方が学べる点で、経営者や管理職にとって重要な一冊だと言えるでしょう。
とにかく仕組み化 ── 人の上に立ち続けるための思考法のみんなのレビュー
Amazonやソーシャルメディアに投稿された実際のレビューを分析しました。良い評価と悪い評価の両方を公平に紹介します。
それぞれ詳しく見ていきましょう。
とにかく仕組み化 ── 人の上に立ち続けるための思考法の良いレビュー
高評価をつけた読者の多くは、組織運営の本質を学べたと評価しています。特に識学シリーズを既に読んでいる人からの支持が高い傾向にあります。
「本書でも触れているように今までの所謂「流行り」の考えとは逆の方向ではあるが、組織として最大価値を出すために最も重要な考え方だと思う。個人として成果を上げるのか、組織としてより大きな成果を上げるのか。組織人であることの考え方を学べる。」
Amazon
「とても参考になる本です。なかなか全部を行う事が難しいとは思いますが、勉強になります。色々取り入れていきたいと思います。」
Amazon
とにかく仕組み化 ── 人の上に立ち続けるための思考法の悪いレビュー
低評価のレビューでは、「具体的な方法論が不足している」「前提知識がないと理解しづらい」という指摘が目立ちます。特に初めて識学に触れる読者からは厳しい評価が寄せられています。
「まずこの本は「仕組み化の為のHowto」では無いという事です。その内容を求めて読むと「内容が薄い」「抽象的で何が言いたいか分からない」という感想になってしまいます。同じ著者の「リーダーの仮面」「数値化の鬼」を先に読み、識学の概念を把握した状態で無ければ読んでいても腹落ちしない部分があります。」
Amazon
「人を責めるなルールを責めろ、仕組み化、これらはわかる。どこに書いてあるんだ?途中から仕組み化の話がなく、むしろ、やる気の出し方など属人化する方法が書かれていて、この本を全面に信じて実践する人が現れるとやばいと思った。」
Amazon
とにかく仕組み化 ── 人の上に立ち続けるための思考法の学びのポイント
本書から得られる学びは、組織マネジメントの本質的な考え方です。具体的なテクニックではなく、思考の軸を学べる点が最大の価値となります。
それぞれ詳しく見ていきます。
学びのポイント1:感情論から脱却した合理的マネジメント
本書の最大の学びは、マネジメントから感情的要素を排除する思考法です。「部下のやる気を引き出す」「チームの絆を深める」といった従来の方法論とは対極にあります。
著者は、人の感情や意欲に頼る組織運営は不安定だと指摘します。誰がやっても同じ成果が出る環境を作ることこそが、真のマネジメントだという考え方は、多くの管理職にとって新たな気づきとなるでしょう。ルールと権限の明確化によって、個人の資質に左右されない組織づくりの本質を学べます。
学びのポイント2:再発防止の根本的アプローチ
「人を責めずルールを責める」という考え方は、問題解決の視点を根本から変える学びです。多くの組織では問題が起きると担当者を叱責しますが、それでは同じ問題が繰り返されます。
本書では、ミスが発生する環境を作っているルールに問題があるという視点を提示します。人の注意力には限界があり、完璧を求めること自体が非合理的です。仕組みとして防げる体制を構築する発想は、組織改善の実務に直結する重要な学びとなります。
学びのポイント3:プレイヤーからマネージャーへの意識改革
リーダー自身が現場の業務をこなすことは、組織にとってマイナスだという主張は、多くの管理職にとって目から鱗の学びです。優秀なプレイヤーほど、自分が動いた方が早いと考えがちです。
しかし本書では、それが部下の成長を妨げ、組織の拡大を阻害すると指摘します。リーダーの仕事は自ら成果を出すことではなく、メンバーが自律的に動ける環境を整えることです。この役割の再定義は、マネジメント職に就いたすべての人が学ぶべき本質的な視点と言えるでしょう。
著者が読者に伝えたいこと
著者の安藤広大氏が本書を通じて最も伝えたいのは、組織運営における思考の転換です。人の善意や努力に依存する経営から、システムとして機能する組織づくりへのパラダイムシフトを促しています。
多くの経営者や管理職が陥る「人材育成」という罠についても言及しています。個々の能力を高めることよりも、誰がやっても成果が出る環境を作ることの方が、組織にとって遥かに重要だというメッセージです。従業員一人ひとりの成長を願う気持ちは尊いものの、それがマネジメントの目的になってはいけないと著者は主張します。
また、リーダーの孤独についても触れています。流行りの経営論とは逆の方向を行く識学の考え方は、周囲の理解を得